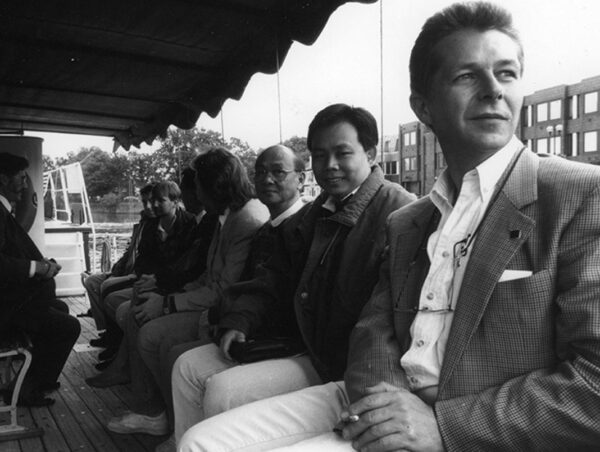MSI JAPANが取り組むアリーナ中が均一な音体験
BARBEE BOYS(バービーボーイズ)は、1980年代に活動した日本のロックバンド。ツインボーカル編成の男女5人で構成されるこのバンドは、当時若い世代に圧倒的な支持を得ていましたが、惜しまれつつも1992年1月、渋谷公会堂でのライブを最後に解散しました。
そのBARBEE BOYSが2020年1月13日、国立代々木競技場第一体育館にてワンマンライブ【突然こんなところは嫌いかい?】を開催することが決定。ファンの間で大変な話題となりました。BARBEE BOYSがワンマンライブを行うのは、2010年3月の日本武道館公演以来10年ぶりだったためです。
この記念すべきワンマンライブのPAを担当したのがMSI JAPAN東京の保手氏です。保手氏はメンバーの杏子さんが所属するオフィスオーガスタのアーティストをこれまでも担当しており、その経緯から今回白羽の矢が立ちました。
保手氏が特別なのは、優れたオペレーターであるのと同時に、優れたシステムテックであるという点にあります。同氏は自身がミックスする本公演のシステムプランを自分自身で設計しました。今回はアリーナ中に均一な音体験を実現するという新しいアプローチのシステムプランについて詳しくお話を聞きました。
均一な音体験をすべてのお客さんに届けるために保手氏のプランは大変ユニークなものでした。H型のタワーの4隅にサブウーファーを含む4アレイが吊られ、それぞれが違う方向を狙っています。ステージに向かって正面向きのメインアレイはMLA 14本(内1本はMLDダウンフィルキャビネット)。そこから45度方向外を向けたサイドアレイはMLA 10本(内1本はMLDダウンフィルキャビネット)。さらにメインアレイに対して90度外側を向いたアレイはMLA 7本(内2本がMLDダウンフィルキャビネット)。この大外狙いのアレイは360度方向に対して90度横を向いているということで「270度」と呼んでいました。これら3アレイはH型タワーのそれぞれの突端に吊るされ、それらの対角にあたる位置にMLXサブウーファー6本(内2本はカーディオイド制御を構成する背面向き)がメインアレイに対し45度ひねった向きで吊られています。
保手氏はこう説明します。「まず大前提として、短時間でのセットアップが必須でした。前日の公演の搬出が終わった午前0時からセットアップ開始。H型のタワーも前日の公演で使用されたものをモーターの位置だけ変えてもらって流用したものです。代々木第一体育館は天井の耐荷重に制限があるため、自立型のタワーで吊元を作る必要があります。タワーを増やさず、バランスよく荷重を検討した結果このような配置になりました。」
MLAは水平90度のスピーカーで、45度ずつ振った角度では多分にオーバーラップが生まれます。270度アレイはどうして必要だったのでしょうか。それは代々木第一体育館の特殊な形状が起因しています。
「代々木第一体育館はエンドステージで使用するとき、メインアレイが狙うべき正面側にはスタンド席がありません。どちらかというとサイドアレイが狙うべき方向に多くのスタンド席があります。今回10年ぶりにBARBEE BOYSがワンマンライブということで多くのお客さんの動員が見込まれました。そこで制作サイドはステージ横いっぱいの位置まで座席とすることを決定したのです。しかしサイドアレイを大きく外に振ることはできません。メインアレイは正面の壁の反射を嫌って、上を向けないため、奥側のスタンド席のカバーはサイドアレイにゆだねられているからです。この場合、ステージ横方向のスタンド席を狙う専用のアレイが必要となるわけです。」
メインアレイの背面で斜め横を向いたサブウーファーがユニークです。これがこのような設置位置になったのはどういう意図なのでしょうか。
すべてのお客さんに同じ体験をしてほしいというのがプランの出発点です。下に設置するサブウーファープランだけでは、アリーナ席は十分な低域が得られますが、スタンド席はどうしても薄くなってしまいます。逆にスタンドでちょうどいいくらいまでサブを上げると、アリーナ席前方のお客さんはものすごい低域になってしまう。10年ぶりのワンマン公演です。スタンドで見ているお客さんにもベースやリズムをちゃんと感じて欲しい。すぐにサブを吊るという発想になりました。」
システムプランの意図は後ろ側のサブウーファーに対してそれぞれ3アレイのディレイを合わせていくというものです。なかなかチューニングの手順が難しそうですがどのような流れになるのでしょうか。
「まずメインアレイと吊ってある後ろ側のサブウーファーでディレイを合わせます。当然メインを遅らせることになるのですが、これは軸上ではなく、少しオフアクシスで調整します。次にアウトサイドをメインと合わせます。ここではメインの高域のみを出して、その指向範囲が途切れる位置を見つけ出し、その少し戻った位置にマイクを立てます。270度も同様の手順で合わせていきます。」
ここが大きくオーバーラップしたアレイ同士をうまく合わせるコツのようです。
「最近、メインアレイにたくさん仕事をさせるチューニングをするように心がけています。理由は2つあって、まずそのほうが会場全体のエネルギーが外に広がらないのでFOHでの反射が減ってオペレートがしやすい。2つ目はそうしたほうがオーバーラップした場所の干渉が少ない。」
なるほどハース効果の理屈でレベルの違うアレイ同士は干渉が起きにくいということのようです。メインアレイをレベル大きめに、サイドアレイや補助アレイをレベル小さめにすることで相互干渉を押さえるというアプローチです。
サブウーファーを吊っている以外にも、ステージセンター前にスタックサブウーファーが一列のサブウーファーアレイを形成していました。横向きのMLXが8本並べられ、その上にリア向きのカーディオイドモードのサブウーファーが1つとばしで合計4か所設置されていました。海外のフェスティバルなどでよく見かけるブロードサイドカーディオイドサブアレイです。
「サブウーファーを吊っただけでは今度はアリーナのお客さんが物足りない。そこでセンターに短いながらもサブアレイを設置することにしました。外側に向けてディレイを深めていくことによって指向性パターンを作り出すサブアークです。Martin AudioのサブウーファーカルキュレータEXELで計算し、最初は狭目の角度でやってみたのですが、システムサポートの紙屋と話し合ってもう少し広げたほうが良いとなりました。結局120度くらいの指向角設定で落ち着いています。グラウンドサブは床面の鏡面効果もあって、吊っているサブウーファーよりは9dBほど小さく出しています。しかしあるのとないのとでは全然結果が違います。」
サブアークを設定する場合のディレイはどのようにしているのでしょうか。
「サブアークの一番外側のサブウーファーとメインでディレイを合わせます。ですから手順としては、先にサブアークの指向角を決めてからでないとチューニングできません。個別のサブウーファー内部のDSPでアークを形成し、これを全体としてディレイをかけてメインに合わせていきます。」
MLAをチョイスするということについて保手氏の意見を聞いてみました。
「私の知る限りMLAは現存するすべてのスピーカーシステムの中で音が一番近く感じるものです。また遠達性も素晴らしい。今回の公演はMLAでなければ成し遂げられなかった。」
一方でMLAの指向性制御をもってしても解決できない部分もあります。たとえば今回の代々木第一体育館のような特殊な形状と客席レイアウトのように。
「プランをうまくすれば無限の可能性を持っているのがMLA。MSIも使い始めたばかりの頃は経験不足で、その良さを最大限発揮できない場面もあった。しかし近年の経験値の蓄積と新しいシステムプランアプローチで、様々な音楽のジャンル、様々なクライアントの需要に合わせて、自在に柔軟に臨むことができると思います。」
時間がないと言いながら、様々な工夫と調整を盛り込んだこのセットアップ。さらに同氏はこのあとリハーサル、本番のオペレーションをこなします。
「寝てないから自分の耳が信用できなくて、若手を呼んで意見をもらいながらオペをやったんだ」
FOHには集まった後輩のエンジニアと楽しく議論しながらリハーサルを進める同氏の姿が。現場には保手氏を慕う若手が多く集まり、活気のある雰囲気が印象的な現場でした。
コンサートは大盛況に終わり、翌週のLINE CUBE SHIBUYA(新渋谷公会堂)の追加公演へと続きます。